▼書評 『人が自分をだます理由ー自己欺瞞の進化心理学』
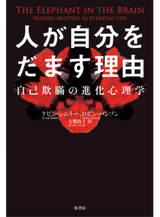 人が自分をだます理由ー自己欺瞞の進化心理学
人が自分をだます理由ー自己欺瞞の進化心理学
著者 ケヴィン・シムラー、ロビン・ハンソン
訳者 大槻 敦子
出版社 原書房
発行 2019 03/05
《本書こそが、人間を人間としてたらしめる理由である》
本書は「進化心理学」からみた、まさにボク達の行動である。本書の原題を直訳すれば「脳の中の象」です。これは、その場にいる誰もが見えているはずなのに見えていないふりをする状態を指し、=「部屋の中の象」という英語の慣用句を踏まえた表現なのだ。しかも誰しも持っているから面白い。
ボク達人類は、隠された動機に基づいて行動しているだけでなく、そうするべく設計されている種です。ボク達の脳は私欲のために行動するよう作られている一方で、他者の前では利己的に見えないように努力するのです。したがって、
なのです。およそ一世紀前の経済および社会学者のソースタイン・ヴェブレンからヒントを得て、さらに大きな社会レベルの隠された動機を探って見つけた、「衒示(げんじ)的消費」。なぜ、高級品バッグなどを買うのかと問われると、消費者は、快適さ、美しさ、機能を強調。しかしながら、実は贅沢品の需要はおもに社会的な動機、すなわち「富を見せびらかす」ためでもあるのです。最近では、書籍「消費資本主義」の著者のジェフリー・ミラーが有名です。さらに、本書では一歩踏み込み人間が無意識に行っている行動を列挙するだけでなく、慈善事業、企業、病院、大学など、重んじられている制度の多くが公式な目的と同時に、隠された目的を果たしていることも示された点でホットといえるでしょう。
人はときに、虐待するⅭEO(最高経営責任者)や女たらしの大統領は別世界の人間で、自分は足が地についていると自画自賛しますが、しかしながら、少なくとも「規範」を回避する方法という点では、その差はおもに程度の問題なのです。自己欺瞞という行為は、平凡な人間で罰を受けずに違反できる行動とも。それは、時に仲間であるべきチームメイトの足を引っ張り、上司にごまをすり、不適切に色目を使って浮気し、策略を巡らし、自分の目的のために他者を操ることさえあります。少なくとも人は、
であるのです。
さらに、本書では自らをだまそうとしているように映る人間を「狂人」、「忠臣」、「チアリーダー」、「詐欺師」タイプに分類し、ボディランゲージ、笑い、会話、消費、芸術、慈善行為、教育、医療、宗教、さらには政治とその動機と、その動機が実はありふれたことで、しかも重要だということを共著の2人が解き明かしていくのです。
では、具体的に「芸術」をみてみよう。芸術はご存知にように時間とエネルギーの両方でコストの高い行動だが、同時に非実用的でもあります。しかしながら、「自然選択によって進化したのか?」、それとも「副産物なのか?」。この論理、実は
をかたきており、つまりは潜在的相手の健康、富、活動力など、その無駄が表している生存の余力に価値がある、すなわち「芸術」は進化心理学者の多くは、人間の二足歩行のそれと同じで「適応」と考えている点です。ここで「芸術」に関する面白い記述をみてみよう!!それが適応度ディスプレイだ。芸術体験には外発的特質が必須である。つまりはその人の技量と証明だ。つまるところ、芸術家と消費者双方にとって成功しているものと、まったく失敗に終わるものとの差は、外発的特質によるものです。
たとえば、ルーブル美術館の防弾ガラスの向こう側にある、レオナルド・ダヴィンチの『モナ・リザ』。実際に足を運んで見た被験者に、仮に『モナ・リザ』が焼けてしまった場合について考えるように求めたら、その8割は見分けがつかないほどよくできたレプリカよりオリジナルの〝灰〝を見たいと答えたそうです。この感想こそ、人間の最たるものではないでしょうか!!
また、金銭にフォーカスされた「慈善の寄付」。アメリカ人の大部分の非営利行為に関心があると述べているが、一年のあいだに何らかの慈善の寄付について調べる人は35%で、アメリカの寄付にうち、それもいちばん必要としている人々、すなわち世界に貧困者に届くのは13%に満たないとも。
さらには、医療においてはどうだろう?!例として、3600人の7年半追跡した調査がある。郊外の居住者は都市部の居住者よりも平均して、6年長生きで、たばこを吸わない人は喫煙者より3年長生き、また少ししか運動しない人より運動を多くする人は15年長生きしたことが報告されています。
それでも何故人々は、費用対効果で健康が改善できるとわっていても日常のライフスタイルには自ら、あまり介入しないのであろう。そこには、もしかすると『「健康第一」にはあまり関心がなく、第三者がよいと考える治療に関心を持っている』。そう言われてみれば、そうかもしれないですね。食事を変えろ、睡眠をとれ、もっと運動をしろ、、こうした小言が重要とわかっていながら、「鯖缶」に頼るなどなど。
本書の進化心理学という学問を知れば、状況認識がうまくなり、間違った選択を減らせるかもしれません。ボクは、ジョン・レノンを言葉を思い出しました。「みんな平和について語るけど、誰もそれを平和的な方法でやってないんだ」と。
心にも環境に適応するための淘汰が起きたとみる、進化心理学の意欲作。大著ですが読み応えタップリです。是非この10連休などに皆さまも手に取って下さいませ。
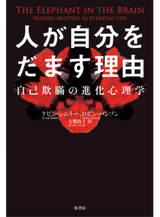 人が自分をだます理由ー自己欺瞞の進化心理学
人が自分をだます理由ー自己欺瞞の進化心理学著者 ケヴィン・シムラー、ロビン・ハンソン
訳者 大槻 敦子
出版社 原書房
発行 2019 03/05
《本書こそが、人間を人間としてたらしめる理由である》
本書は「進化心理学」からみた、まさにボク達の行動である。本書の原題を直訳すれば「脳の中の象」です。これは、その場にいる誰もが見えているはずなのに見えていないふりをする状態を指し、=「部屋の中の象」という英語の慣用句を踏まえた表現なのだ。しかも誰しも持っているから面白い。
ボク達人類は、隠された動機に基づいて行動しているだけでなく、そうするべく設計されている種です。ボク達の脳は私欲のために行動するよう作られている一方で、他者の前では利己的に見えないように努力するのです。したがって、
みずからを欺く自己欺瞞は、好ましくない振る舞いをしながら「よく見せる」ために脳が用いる策略であり戦略
なのです。およそ一世紀前の経済および社会学者のソースタイン・ヴェブレンからヒントを得て、さらに大きな社会レベルの隠された動機を探って見つけた、「衒示(げんじ)的消費」。なぜ、高級品バッグなどを買うのかと問われると、消費者は、快適さ、美しさ、機能を強調。しかしながら、実は贅沢品の需要はおもに社会的な動機、すなわち「富を見せびらかす」ためでもあるのです。最近では、書籍「消費資本主義」の著者のジェフリー・ミラーが有名です。さらに、本書では一歩踏み込み人間が無意識に行っている行動を列挙するだけでなく、慈善事業、企業、病院、大学など、重んじられている制度の多くが公式な目的と同時に、隠された目的を果たしていることも示された点でホットといえるでしょう。
人はときに、虐待するⅭEO(最高経営責任者)や女たらしの大統領は別世界の人間で、自分は足が地についていると自画自賛しますが、しかしながら、少なくとも「規範」を回避する方法という点では、その差はおもに程度の問題なのです。自己欺瞞という行為は、平凡な人間で罰を受けずに違反できる行動とも。それは、時に仲間であるべきチームメイトの足を引っ張り、上司にごまをすり、不適切に色目を使って浮気し、策略を巡らし、自分の目的のために他者を操ることさえあります。少なくとも人は、
救いがたいほど自己本位ではないが、気高い行動基準に求めらるレベルよりは自分勝手
であるのです。
さらに、本書では自らをだまそうとしているように映る人間を「狂人」、「忠臣」、「チアリーダー」、「詐欺師」タイプに分類し、ボディランゲージ、笑い、会話、消費、芸術、慈善行為、教育、医療、宗教、さらには政治とその動機と、その動機が実はありふれたことで、しかも重要だということを共著の2人が解き明かしていくのです。
では、具体的に「芸術」をみてみよう。芸術はご存知にように時間とエネルギーの両方でコストの高い行動だが、同時に非実用的でもあります。しかしながら、「自然選択によって進化したのか?」、それとも「副産物なのか?」。この論理、実は
時間やエネルギーなどの資源を無駄にすることのできる相手のほうが交配相手として好ましいという考え方
をかたきており、つまりは潜在的相手の健康、富、活動力など、その無駄が表している生存の余力に価値がある、すなわち「芸術」は進化心理学者の多くは、人間の二足歩行のそれと同じで「適応」と考えている点です。ここで「芸術」に関する面白い記述をみてみよう!!それが適応度ディスプレイだ。芸術体験には外発的特質が必須である。つまりはその人の技量と証明だ。つまるところ、芸術家と消費者双方にとって成功しているものと、まったく失敗に終わるものとの差は、外発的特質によるものです。
たとえば、ルーブル美術館の防弾ガラスの向こう側にある、レオナルド・ダヴィンチの『モナ・リザ』。実際に足を運んで見た被験者に、仮に『モナ・リザ』が焼けてしまった場合について考えるように求めたら、その8割は見分けがつかないほどよくできたレプリカよりオリジナルの〝灰〝を見たいと答えたそうです。この感想こそ、人間の最たるものではないでしょうか!!
また、金銭にフォーカスされた「慈善の寄付」。アメリカ人の大部分の非営利行為に関心があると述べているが、一年のあいだに何らかの慈善の寄付について調べる人は35%で、アメリカの寄付にうち、それもいちばん必要としている人々、すなわち世界に貧困者に届くのは13%に満たないとも。
さらには、医療においてはどうだろう?!例として、3600人の7年半追跡した調査がある。郊外の居住者は都市部の居住者よりも平均して、6年長生きで、たばこを吸わない人は喫煙者より3年長生き、また少ししか運動しない人より運動を多くする人は15年長生きしたことが報告されています。
それでも何故人々は、費用対効果で健康が改善できるとわっていても日常のライフスタイルには自ら、あまり介入しないのであろう。そこには、もしかすると『「健康第一」にはあまり関心がなく、第三者がよいと考える治療に関心を持っている』。そう言われてみれば、そうかもしれないですね。食事を変えろ、睡眠をとれ、もっと運動をしろ、、こうした小言が重要とわかっていながら、「鯖缶」に頼るなどなど。
本書の進化心理学という学問を知れば、状況認識がうまくなり、間違った選択を減らせるかもしれません。ボクは、ジョン・レノンを言葉を思い出しました。「みんな平和について語るけど、誰もそれを平和的な方法でやってないんだ」と。
心にも環境に適応するための淘汰が起きたとみる、進化心理学の意欲作。大著ですが読み応えタップリです。是非この10連休などに皆さまも手に取って下さいませ。
このブログにコメントするにはログインが必要です。
さんログアウト
この記事には許可ユーザしかコメントができません。