▼書評 『まちづくり都市金沢』
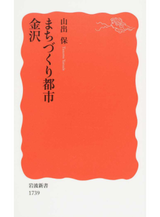 まちづくり都市金沢
まちづくり都市金沢
著者 山出 保
出版社 岩波書店
発行 2018 09/20
《粋なまち、訪れてみたい金沢》
以前、書籍『おどろきの金沢』を読みましたが、その著者の視点は本書より観光的な側面が描かれていました。本書はより実務的です。それもそのはず、著者は金沢市市長を5期20年の在職経験者です。「金沢」、勝ち組・負け組という言葉がありますが、完全なる勝ち組の街ですね。決して驕れることなく、市民との意見を重んじいるのが本書からまざまざと垣間見えます。
北陸新幹線〈長野ー金沢間〉が開業し、いまや東京ー金沢間は最速で2時間28分、さらには2016年11月には仙台-金沢間に大宮駅での乗り換えなしで初となる直通新幹線が臨時に運行されているとのことです。注目の街・「粋」な金沢。対して「雅」の京都です。
実は、金沢は街の基礎ができてから430年余り、一度も戦禍に遭ったことのない平和の街です。東洋では金沢、ヨーロッパではチューリッヒになります。前述を著者は「歴史に責任をもつまち」と記述しています。上述の平和の歴史を含め、文化、自然、産業など観光関連のステークホルダー多岐にわたり、多様な主体、マネジメントが非常に市政に圧し掛かります。とりわけ、観光のケースでは著者は繰り返し「自制の論理」なる言葉を用いています。
と。たとえば、いま、金沢の商業の販売面で困りごとのひとつは、いたずらに「金沢」を名乗る商品が目につくこと。金沢ブランドが傷つきかねない事態にどう対処するか、商品に「金沢」を冠する場合の条件設定に、行政と業界の検討が求められると。他にも心ない外部資本の進出etc.. と小職は冒頭で勝ち組を述べましたが、ともすれば複合施設などやみくもに建設しガンガン儲けたいところ、しかし著者の都市美に対する熱意には頭が下がりました。
保存と開発、伝統と現代、これらは、いずれも矛盾する概念です。それを石川県が生んだ哲学者、仏教哲学者2人の思想から着想を得ます。ひとりが西田幾多郎、もうひとりが金沢市出身の鈴木大拙です。
その思想とは「矛盾の対立」です。現実の世界は、さまざまな面において無限な弁証法的な過程から成立する、そこでの矛盾は、一つの全体でもある。ゆえに、まちづくり都市金沢は、
金沢というまちは、歴史の真実において、あるいは現実のあらゆる場面で、同時存在的に相いれないものを内包している。まつづくり、文化であれ、二律背反し矛盾する概念に遭遇する。
「城下町金沢の文化遺産群と文化的景観」をテーマに文化庁へ世界遺産登録の申請をしたのが2006(平成18)年のこと。しかし登録の暫定リスト入りせずでした。その理由(わけ)は、近世日本の城下町の代表例、典型例として普遍的価値を持つことの証明が不十分であったことになります。
著者からして、景観保存で参考になるのが、滋賀県の彦根市、城下町・商人町の長浜市、商人町の近江八幡市、瀬戸川と白壁土蔵街の飛騨市古川市などと挙げております。
と。本書に至る所に「住民」本位の姿勢が綴られています。たとえば、主計町、下石引町、木倉町など観光目的で昔から伝わってきた町名を復活したのではありません。地域のコミュニティ=連帯感を強化し、「自分たちがこんなに歴史のある町」と感じ、その誇りを胸に、「みんなで力で合わせて住みよいまちづくりに励みましょう」と始めたものです。即ち、連帯感とは高齢者の「孤独」対策にもなるのです。
とかく、経済効率・経済原理で建て直す、なんて叫ばれますが、「市政」というのはそう単純ではかりません。矛盾と葛藤の生き様を本書でご体験下さいませ。
小職の住む街においては、太陽光パネルの乱立が顕著です。隣町も同様です。眺望景観や俯瞰景観は必ずや本書から学べる点もあると思います。
行政に携わる方、地方創生にご興味のある方には、とりわけおススメの一冊です。
【関連書籍】
 外国人が見た日本-「誤解」と「再発見」の観光150年史
外国人が見た日本-「誤解」と「再発見」の観光150年史
著者 内田 宗治
出版社 中央公論新社
発行 2018 10/25
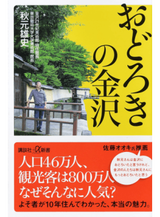 おどろきの金沢
おどろきの金沢
著者 秋元 雄史
出版社 講談社+α新書
発行 2017 06/21
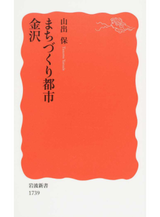 まちづくり都市金沢
まちづくり都市金沢著者 山出 保
出版社 岩波書店
発行 2018 09/20
《粋なまち、訪れてみたい金沢》
以前、書籍『おどろきの金沢』を読みましたが、その著者の視点は本書より観光的な側面が描かれていました。本書はより実務的です。それもそのはず、著者は金沢市市長を5期20年の在職経験者です。「金沢」、勝ち組・負け組という言葉がありますが、完全なる勝ち組の街ですね。決して驕れることなく、市民との意見を重んじいるのが本書からまざまざと垣間見えます。
北陸新幹線〈長野ー金沢間〉が開業し、いまや東京ー金沢間は最速で2時間28分、さらには2016年11月には仙台-金沢間に大宮駅での乗り換えなしで初となる直通新幹線が臨時に運行されているとのことです。注目の街・「粋」な金沢。対して「雅」の京都です。
実は、金沢は街の基礎ができてから430年余り、一度も戦禍に遭ったことのない平和の街です。東洋では金沢、ヨーロッパではチューリッヒになります。前述を著者は「歴史に責任をもつまち」と記述しています。上述の平和の歴史を含め、文化、自然、産業など観光関連のステークホルダー多岐にわたり、多様な主体、マネジメントが非常に市政に圧し掛かります。とりわけ、観光のケースでは著者は繰り返し「自制の論理」なる言葉を用いています。
「自分ひとり儲かれば」、「自分だけ目立てば」という考えは成り立たない。近江市場をつくったとされる近江商人の商売の基本は三方よし「売りてよし、買い手よし、世間よし」にあったことをあらためて思い出したい
と。たとえば、いま、金沢の商業の販売面で困りごとのひとつは、いたずらに「金沢」を名乗る商品が目につくこと。金沢ブランドが傷つきかねない事態にどう対処するか、商品に「金沢」を冠する場合の条件設定に、行政と業界の検討が求められると。他にも心ない外部資本の進出etc.. と小職は冒頭で勝ち組を述べましたが、ともすれば複合施設などやみくもに建設しガンガン儲けたいところ、しかし著者の都市美に対する熱意には頭が下がりました。
保存と開発、伝統と現代、これらは、いずれも矛盾する概念です。それを石川県が生んだ哲学者、仏教哲学者2人の思想から着想を得ます。ひとりが西田幾多郎、もうひとりが金沢市出身の鈴木大拙です。
その思想とは「矛盾の対立」です。現実の世界は、さまざまな面において無限な弁証法的な過程から成立する、そこでの矛盾は、一つの全体でもある。ゆえに、まちづくり都市金沢は、
金沢というまちは、歴史の真実において、あるいは現実のあらゆる場面で、同時存在的に相いれないものを内包している。まつづくり、文化であれ、二律背反し矛盾する概念に遭遇する。
つねに矛盾と向き合い、その対応に思慮をめぐらし、矛盾を超えていく、苦しみを喜びに変えていく、そんなまちでもある。
「城下町金沢の文化遺産群と文化的景観」をテーマに文化庁へ世界遺産登録の申請をしたのが2006(平成18)年のこと。しかし登録の暫定リスト入りせずでした。その理由(わけ)は、近世日本の城下町の代表例、典型例として普遍的価値を持つことの証明が不十分であったことになります。
著者からして、景観保存で参考になるのが、滋賀県の彦根市、城下町・商人町の長浜市、商人町の近江八幡市、瀬戸川と白壁土蔵街の飛騨市古川市などと挙げております。
地歩を固めつつ、時流に流されない、また、まちはすぐには変化しない。だからこそ持続的発展につながるまちづくりでなければなりません
と。本書に至る所に「住民」本位の姿勢が綴られています。たとえば、主計町、下石引町、木倉町など観光目的で昔から伝わってきた町名を復活したのではありません。地域のコミュニティ=連帯感を強化し、「自分たちがこんなに歴史のある町」と感じ、その誇りを胸に、「みんなで力で合わせて住みよいまちづくりに励みましょう」と始めたものです。即ち、連帯感とは高齢者の「孤独」対策にもなるのです。
とかく、経済効率・経済原理で建て直す、なんて叫ばれますが、「市政」というのはそう単純ではかりません。矛盾と葛藤の生き様を本書でご体験下さいませ。
小職の住む街においては、太陽光パネルの乱立が顕著です。隣町も同様です。眺望景観や俯瞰景観は必ずや本書から学べる点もあると思います。
行政に携わる方、地方創生にご興味のある方には、とりわけおススメの一冊です。
【関連書籍】
 外国人が見た日本-「誤解」と「再発見」の観光150年史
外国人が見た日本-「誤解」と「再発見」の観光150年史著者 内田 宗治
出版社 中央公論新社
発行 2018 10/25
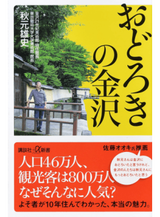 おどろきの金沢
おどろきの金沢著者 秋元 雄史
出版社 講談社+α新書
発行 2017 06/21
このブログにコメントするにはログインが必要です。
さんログアウト
この記事には許可ユーザしかコメントができません。