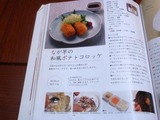■ノーベル賞はこうして決まる -選考者が語る自然科学三章の真実
 ノーベル賞はこうして決まる
ノーベル賞はこうして決まる
著者 アーリング・ノルビ
訳者 千葉 喜久枝
出版社 創元社
発行 2011 11/10
以前、本ブログの2011.12.21付け書籍「パラダイムでたどる科学の歴史」は、「誰が後継者に一番影響があった研究か」に主眼が置かれた書籍であった。
しかし、ノーベル賞は文字通り研究の歴史を遡り、研究の発展において本当に貢献したのは誰であったのかを突き止める点になる。
それはアルフレッド・ノーベルの遺書に基づき100年以上不変である。だからこそ12月10日のあの舞台は、まさに体験した方しかわからないものであろう。
本来であれば、五章あるノーベル賞。本書は、文学章・平和章ではアーネスト・ヘミングウェイしか記されていない。また本書をきっかけに「野口英世アフリカ賞」が小泉政権時代に設立されていた事をWSJ(02.21)に初めて知った。
著者は、ウィルス学者でスゥーデンのカロリンスカ研究所での研究やスゥーデン王立科学アカデミーの事務総長を歴任し30年近くこの偉大なる舞台裏を知る立場にあった。
《偉大なる発見の種はつねにわれわれのまわりをただよっているが、それを受け入れる準備が整っている心にしか根をおろさない》 (科学者 ジョセフ・ヘンリー)
物理学、化学、生理学医学の2009年までの受賞者に、まずは驚かされた。この三章のうち世界の僅か0.25%のユダヤ系人が実に1/4で章を受章しているのだ。これは人間の、また「進化」という学習の仕切り直しである。そして、もうひとつ選考関連の資料は、50年の月日を待たなければならないのが決まりだ。
親子で受賞したケースは過去6例。初めてノーベル賞へ推薦された年に受賞したり、外部からの推薦がないまま委員会内の声で受賞が決まったりした例もある。一度賞が決まれば覆される事は決してない。
また、「運」というものもつきもので、たまたま科学の潮目にあったり、選考に関わる人々の力学も働く。
その代表例が、野口英世といってもいいだろう。もう少し早く顕微鏡が発明されていたら・・
他方、利根川進氏は「多様な抗体で生成する遺伝的な発見により」1987年生物医学賞を受賞した。
本書の最終賞は、著者が関与した牛海綿状脳症(BSE)の原因と知られるプリオンの発見についてのエピソードが、化学に疎いボクにとって一番興味を引いた。
その人物は、博学な永遠の旅行者、カールトン・ガイジュシェクである。
ニューギニアのフォレ族を研究し、それが後々CJD(クロイツフェルト・ヤコブ病)の発見へとつながり、著者はこの人物に追っかけ記者のように同行する。ここがボクにとっての読みどころであった。
そして、カールトン・ガイジュシェクの自宅には、氏のお気に入りになんと野口英世の名が。旅行科学者だっただけにアフリカできっと野口の功績を評価したのであろう。
誰の発見が受賞に値するのか?研究史において、最も重要な発見や概念の構築に貢献されたのは誰であるか?科学が進歩すればすればするほど、選考者にもプレッシャーが重くのしかかる。
現在、ノーベル賞に一番近い人物と言えば、京都大学のips細胞研究の山中氏ではなかろうか?
是非、12月10日オスロの舞台に立っていただきたい。
この書籍で再認識できたのは、ウィルスは確実に人間の進化をもたらした。
そしてボク個人としては、文学・平和賞に特化した書籍を望みたい。
尚、スウェーデン語からの翻訳のため訳者の苦労が窺え、よっ化学の基礎知識を持ち得た方はより一層本書を楽しめるではないだろうか。
 ノーベル賞はこうして決まる
ノーベル賞はこうして決まる著者 アーリング・ノルビ
訳者 千葉 喜久枝
出版社 創元社
発行 2011 11/10
以前、本ブログの2011.12.21付け書籍「パラダイムでたどる科学の歴史」は、「誰が後継者に一番影響があった研究か」に主眼が置かれた書籍であった。
しかし、ノーベル賞は文字通り研究の歴史を遡り、研究の発展において本当に貢献したのは誰であったのかを突き止める点になる。
それはアルフレッド・ノーベルの遺書に基づき100年以上不変である。だからこそ12月10日のあの舞台は、まさに体験した方しかわからないものであろう。
本来であれば、五章あるノーベル賞。本書は、文学章・平和章ではアーネスト・ヘミングウェイしか記されていない。また本書をきっかけに「野口英世アフリカ賞」が小泉政権時代に設立されていた事をWSJ(02.21)に初めて知った。
著者は、ウィルス学者でスゥーデンのカロリンスカ研究所での研究やスゥーデン王立科学アカデミーの事務総長を歴任し30年近くこの偉大なる舞台裏を知る立場にあった。
《偉大なる発見の種はつねにわれわれのまわりをただよっているが、それを受け入れる準備が整っている心にしか根をおろさない》 (科学者 ジョセフ・ヘンリー)
物理学、化学、生理学医学の2009年までの受賞者に、まずは驚かされた。この三章のうち世界の僅か0.25%のユダヤ系人が実に1/4で章を受章しているのだ。これは人間の、また「進化」という学習の仕切り直しである。そして、もうひとつ選考関連の資料は、50年の月日を待たなければならないのが決まりだ。
親子で受賞したケースは過去6例。初めてノーベル賞へ推薦された年に受賞したり、外部からの推薦がないまま委員会内の声で受賞が決まったりした例もある。一度賞が決まれば覆される事は決してない。
また、「運」というものもつきもので、たまたま科学の潮目にあったり、選考に関わる人々の力学も働く。
その代表例が、野口英世といってもいいだろう。もう少し早く顕微鏡が発明されていたら・・
他方、利根川進氏は「多様な抗体で生成する遺伝的な発見により」1987年生物医学賞を受賞した。
本書の最終賞は、著者が関与した牛海綿状脳症(BSE)の原因と知られるプリオンの発見についてのエピソードが、化学に疎いボクにとって一番興味を引いた。
その人物は、博学な永遠の旅行者、カールトン・ガイジュシェクである。
ニューギニアのフォレ族を研究し、それが後々CJD(クロイツフェルト・ヤコブ病)の発見へとつながり、著者はこの人物に追っかけ記者のように同行する。ここがボクにとっての読みどころであった。
そして、カールトン・ガイジュシェクの自宅には、氏のお気に入りになんと野口英世の名が。旅行科学者だっただけにアフリカできっと野口の功績を評価したのであろう。
誰の発見が受賞に値するのか?研究史において、最も重要な発見や概念の構築に貢献されたのは誰であるか?科学が進歩すればすればするほど、選考者にもプレッシャーが重くのしかかる。
現在、ノーベル賞に一番近い人物と言えば、京都大学のips細胞研究の山中氏ではなかろうか?
是非、12月10日オスロの舞台に立っていただきたい。
この書籍で再認識できたのは、ウィルスは確実に人間の進化をもたらした。
そしてボク個人としては、文学・平和賞に特化した書籍を望みたい。
尚、スウェーデン語からの翻訳のため訳者の苦労が窺え、よっ化学の基礎知識を持ち得た方はより一層本書を楽しめるではないだろうか。